2008年10月の週末・・・・バルバレスコは賑やかです。
「BARBARESCO WEEK-END」と題し、毎週30ものバルバレスコ近辺のワイナリーのワインを試飲できるイベントが開催されています。
私が仕事の合間に訪れることができた、10月最後の日曜日。
全てのワインが2005年もの
その中でも私好みの美味しいワインは・・・。
 MOCCAGATTA Bric Balin
MOCCAGATTA Bric Balin
![]() MARCHESI DI GRESY Camp Gros
MARCHESI DI GRESY Camp Gros
![]() CERETTO Bernardot
CERETTO Bernardot
![]() CECILIA MONTE Serracapelli
CECILIA MONTE Serracapelli
![]() CIGLIUTI Serraboella
CIGLIUTI Serraboella
![]() BOFFA CARLO Vitalotti
BOFFA CARLO Vitalotti
![]() CASTELLO DI NEIVE Santo Stefano
CASTELLO DI NEIVE Santo Stefano
![]() FONTANA BIANCA Sori Burdin
FONTANA BIANCA Sori Burdin












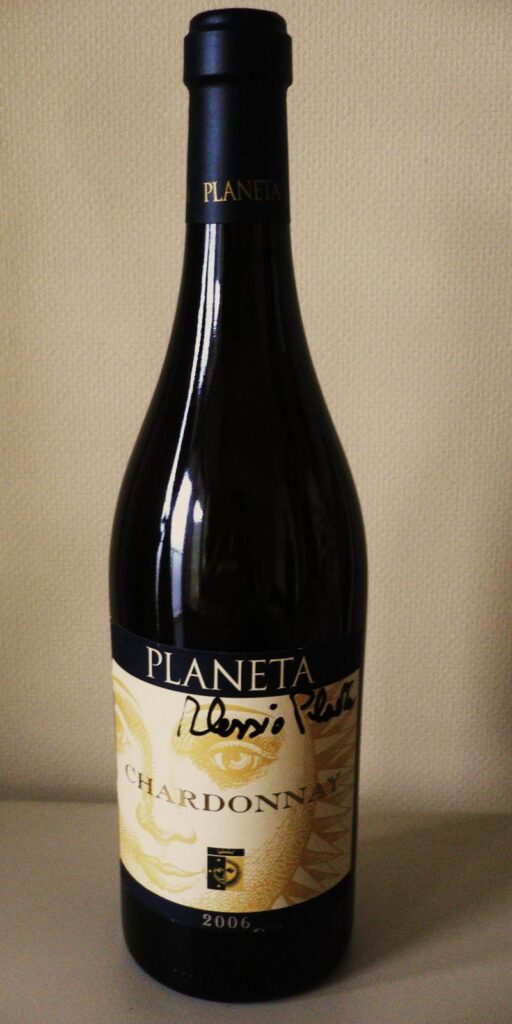
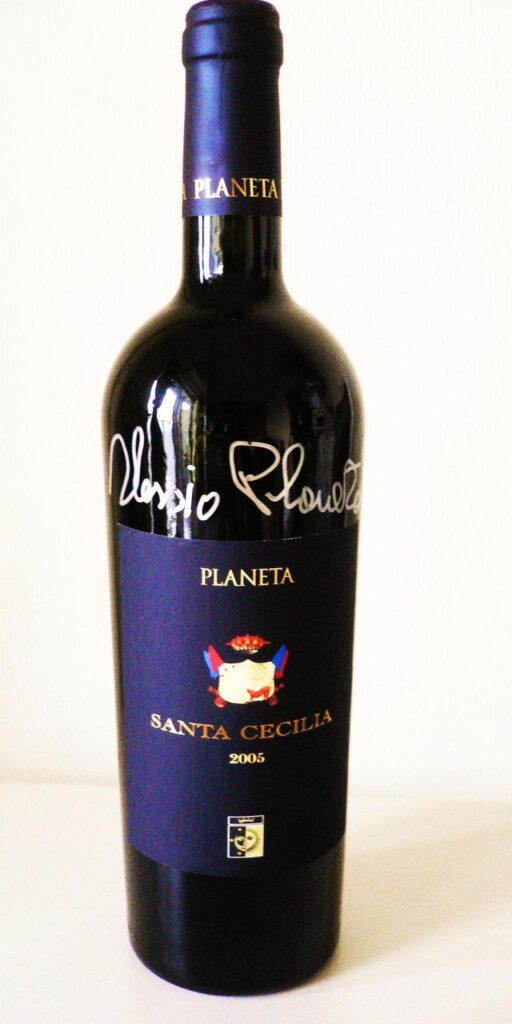



 イタリア貿易振興会事務所長
イタリア貿易振興会事務所長 。
。 で、醸造者によって方法もさまざまだと思いますが、ワインを造る一般的な行為として、醸造段階で酸化防止剤(亜硫酸塩)を添加することは、伝統的な手法でもあるし、ワインは酸化に弱いので酸化防止剤を加えることにより、腐敗を防ぎ、長期保存ができると思うんです・・・。
で、醸造者によって方法もさまざまだと思いますが、ワインを造る一般的な行為として、醸造段階で酸化防止剤(亜硫酸塩)を添加することは、伝統的な手法でもあるし、ワインは酸化に弱いので酸化防止剤を加えることにより、腐敗を防ぎ、長期保存ができると思うんです・・・。