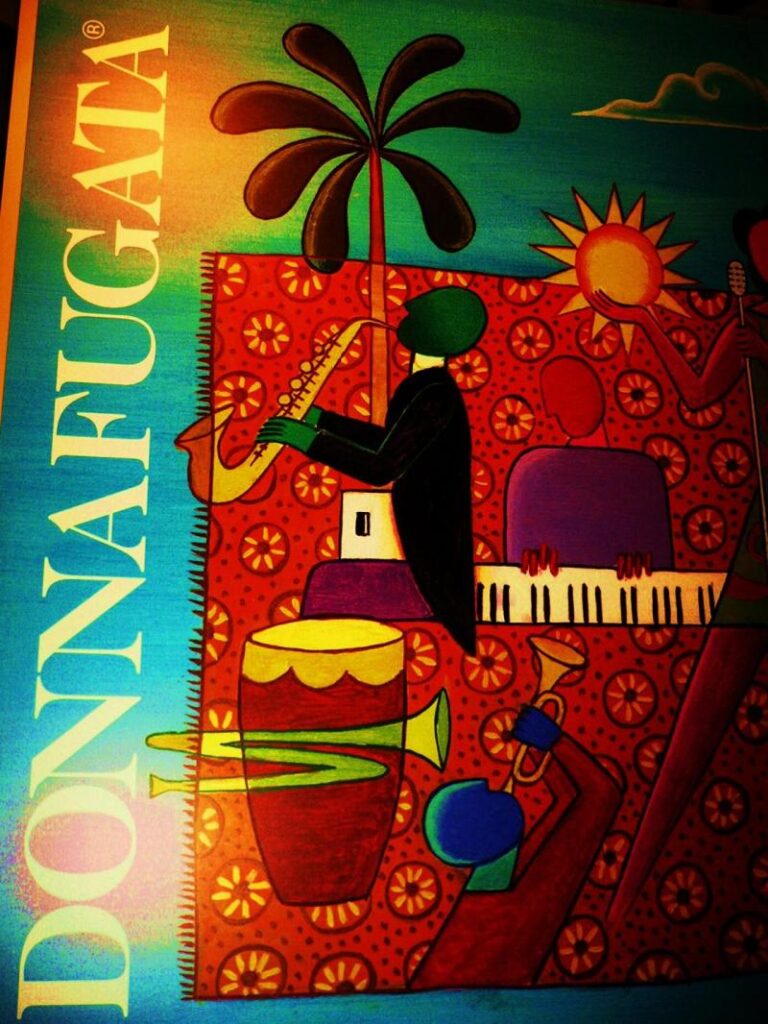太陽の燦々と輝く南イタリア、シチリア島。そのシチリアワインで、昔から大好きなワイナリーがあるんです。
何といっても、味、コストパフォーマンスの良さそして、何とも言えぬ奇抜なデザインのラベル。
そのワイナリーの名は、「DONNA FUGATA(ドンナフガータ)」。このワイナリーは、パレルモ県から、内陸へ80KM程の、コンテッサ・エンテッリーナとゆう場所にあります。
ドンナフガータとゆう名称は、タイトルにもあるように、「逃避する女」を意味し、その名称は1799年のナポレオンが仕掛けた、第二イタリア戦争に遡り・・・・ナポリ王国のブルボン家、フェルナンド四世の妻、ハプスブルグ家のマリア・カロリーナ王妃が、ナポレオン軍の襲来を恐れ、このコンテッサ・エンテッリーナの宮殿に逃避したとゆう物語に由来するものだそうです。
その中でも好きなのが、左端の MILLE E UNA NOTTE (ミッレ エ ウナ ノッテ)。
MILLE E UNA NOTTEは、ネロ・ダーヴォラ種90%使用されて、フレンチバリックで、16か月熟成後、瓶熟成を12カ月。
菫や、ブラックチェリー、それからスパイシーな香りも・・・・程良いタンニン、余韻は持続性有り。
MILLE E UNA NOTTEとは、日本語で千夜一夜物語。
ラベルのデザインは、先ほどの、王妃が逃亡の際、隠れていた宮殿をモチーフに描かれており、そして、その右隣のラベルに描かれている女性が、千夜一夜物語の主人公とゆうことだそう。
ワインを味わうだけでなく、そのワインに付けられた名称、ラベルに纏わるエピソードやデザイン、そういった事も知りながら飲める楽しさが、イタリアワインにはありますよね。

![]()

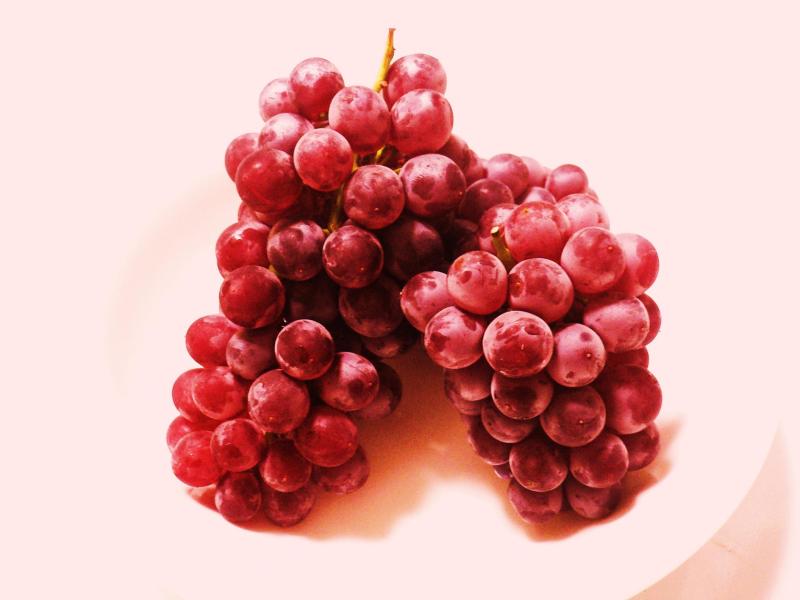
 イタリア
イタリア