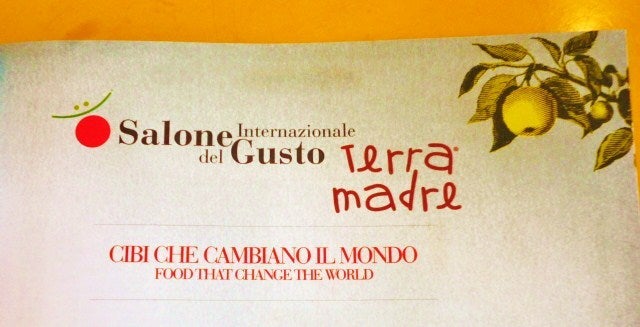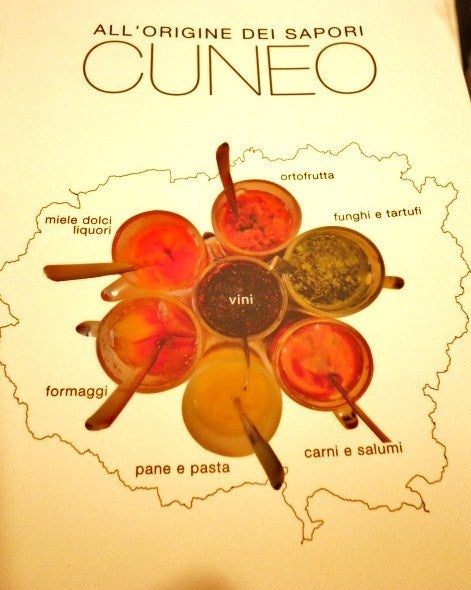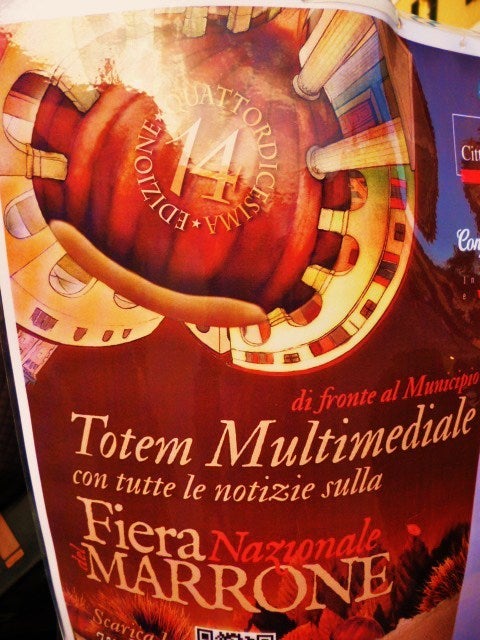若者がストラッキーノチーズを懸命にちぎり作っていたフォカッチャ・ディ・レッコ。
長蛇の列。美味しいもんはイタリア人でも並ぶ。出来立て熱々はほんとに絶品。

テスタローリ。
古代ローマ時代には作られていた粉もん料理の中で最も古いものとされている、トスカーナ最北端ル二ジャー
地方に伝わる厚焼きのクレープのようなパスタ。
このように焼いたものを、一口サイズに切り分けてから茹でソースとからめて食す。
トスカーナ料理ですが、ソースはバジルペーストで食すのが定番。
東リグーリアのラ・スペッツィア県では良く見かけるパスタ料理。

南チロル、アルト・アディジェ州は私がイタリアの中でも最も愛する(出来れば住んでみたい!)地域、そこからは民族衣装を着ての出店もありましたよ。
グリッジョ・アルピーナという品種の乳牛から作られたじっくり2年間熟成された旨みやコクが凝縮された伝統的チーズ「FIOR di BOSCO.(フィオール・ディ・ボスコ」。
フィオール・ディ・ボスコは森の花という意味。なんとも可愛らしいネーミングのチーズですね。

こちらも南チロルより、羊毛品の実演。
南チロルで最古の品種の羊毛のみを使うんだそうです。
アルプスの冬の厳しい寒さの中で生まれた伝統工芸品。
シニョーラがひたすら成形し続けていました。

水をかけながら、ブラシと手で成形し続けること2時間・・・・・一足の羊毛フェルトの靴の完成。
手を真っ赤にさせながら成形していく実に根気のいる作業です。
この伝統を受け継げる若者が後どれくらいいるんかな・・・・・。

トスカーナ産のシガロ(葉巻)の実演もやっていました。
イタリアはヨーロッパの中で最初に葉巻を生産した国でもあります。
一枚一枚葉を広げて包んでいく作業は大変。
物凄い(良い香り)が辺りを包み込みしばし立ち止まりその作業に見入ってしまいました。

イタリア北東部、フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州の生ハム「サン・ダニエーレ」。
パルマの生ハムより塩味も上品で口の中に広がる旨みがなんともいえない大好きな生ハム。
グリッシーニを手にとり、スライスしたてを巻きつけてくれました。

ロンバルディア州の中で一番好きな地域、北部にあるヴァルテッリーナ地方。
大好きな友人の出身地でもあり、特に思い入れのある渓谷のひとつ。
良質な赤ワインの「スフォルツァート」や、蕎麦粉を使ったパスタ「ピッツォケリ」や牛の生ハム「ブレザオラ」等伝統料理の宝庫でもあるこの地方で作られているチーズ、BITTO(ビット)。
2008年ものの試食もありました。このナチュラル・ティスティング 美味しさに脱帽
美味しさに脱帽

アブルッツォ州からこんな可愛らしいスカモルツァチーズもお目見え。食べやすいマイルドな味。

バルサミコ酢(バルサミコにワインビネガーやカラメルを加えて酸味を調節可能な大量生産型)と、フラスコ型にしか瓶詰め出来ない「伝統」と称す事が可能なバルサミコ酢の熟成方法や規定の違いを力説されておりました。

ガルダ湖近郊で生まれたシトロン飲料、チェドラータ。
老舗メーカー「TASSONI」の炭酸飲料は60年代大ヒットした商品。
柑橘類宝庫の瀬戸内で生まれ育った私にとり、この爽やかな香りはたまらん!

シチリア島南東部ラグーザ県、ジアッラターナの巨大玉葱。
スライスして煮たものが瓶詰めされていました。
濃厚な甘み、ブルスケッタに合いそう!魚のマリネなんかのせたら美味しそうだなぁ。

TISANA(ハーブティー)も豊富に。
就寝前にハーブティーを飲む習慣の私。
効能はさまざまで、その日の体調に合わせ飲むとほんとにぐっすり休める私の必需品。

世界各国から集められたスパイスの数々。

会場内を飾るオブジェもイタリアならではの思考で楽しみのひとつ。
こういう食のイベントに来てみると、改めてイタリアの地方色豊か食文化や歴史的背景、探究心がますますくすぶられてきます。
イタリアに行ってみよう!と決心し旅立ったあの時の気持ちと全くぶれててない今があり・・・・。
イタリア食材の素晴らしさに再感動する今日このごろ。
そして皆で守りつづけていかなければ・・・・・。