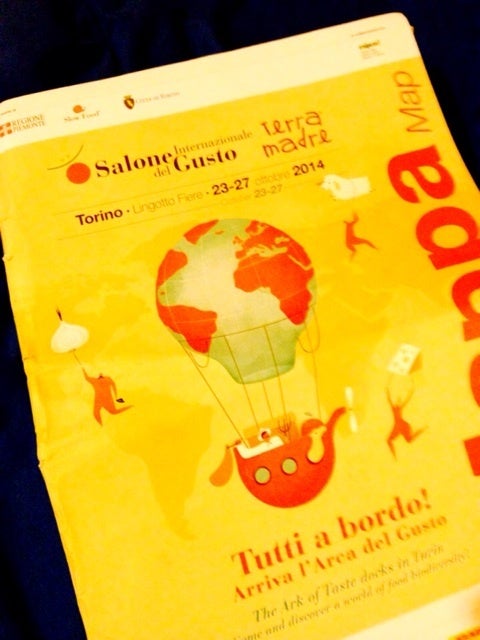今回訪れたワイナリーは、「MALVIRA’」 マルヴィラ社。
1950年代にダモンテ家により創業、現当主でもあるロベルトさんは醸造家でもあり、1廃墟化した別荘を10年前に改装し、レストラン兼プティホテル「VILLA TIBOLDI (ヴィッラ・ティボルディ)」とし蘇らせ、テラスからは丘一面に広がる彼らの手入れの行き届いたクリュ葡萄畑「トリニタ」が眼下に広がり、何とも優雅なひと時を堪能~!
まずはテラスにてスプマンテ片手に畑の由来やこの地についてを説明してくれ、ロベルトさんも同席での食事とマルヴィラワインとのアビナメント(組み合わせ)を。
飲ませていただいたワイン・・・・・満足です。簡潔には書きたくなので、折を見てじっくり向き合い紹介することにします。
全てのエチケットには、ロエロ地区のシンボル「馬車の車輪」にタロットカードの大地や月のを組み合わせた大地の恵み、豊作を祈願したものが・・・・。視覚からも楽しませてくれる、イタリアワインのバラエティーに富んだエチケット。
白トリュフは木の根元の地下40cm位の深さに育ち、海抜700以下のシリカを含む石灰質、粘土質土壌で酸素濃度が高い土地に生育し、アルバ近郊南下しリグーリア州境、ボルミダ渓谷が名高い産地で、高品質な白トリュフの旬は11月中旬から12月にかけて、丁度トリュフ市が終わった頃から、近郊レストランにトリュフ名人達は採れたて白トリュフ卸しに!
その奥には歴代使用されてきた数々の銅製の釜がずらりと並び、暫くし案内人が地下のグラッパ工房を案内してくれ、運ばれてきたばかりのバルベーラのヴィナッチャ(葡萄搾りかす)や、非連続式の蒸気釜、2%のアルコールが蒸発しているバリックの熟成室で噎せ返ったり、グラッパ好きなら是非一度ベルタ社の蒸留所見学はおすすめ!
試飲はバルベーラとネッビオーロで造られた、木樽熟成、1年もの、10年もの、20年ものを。