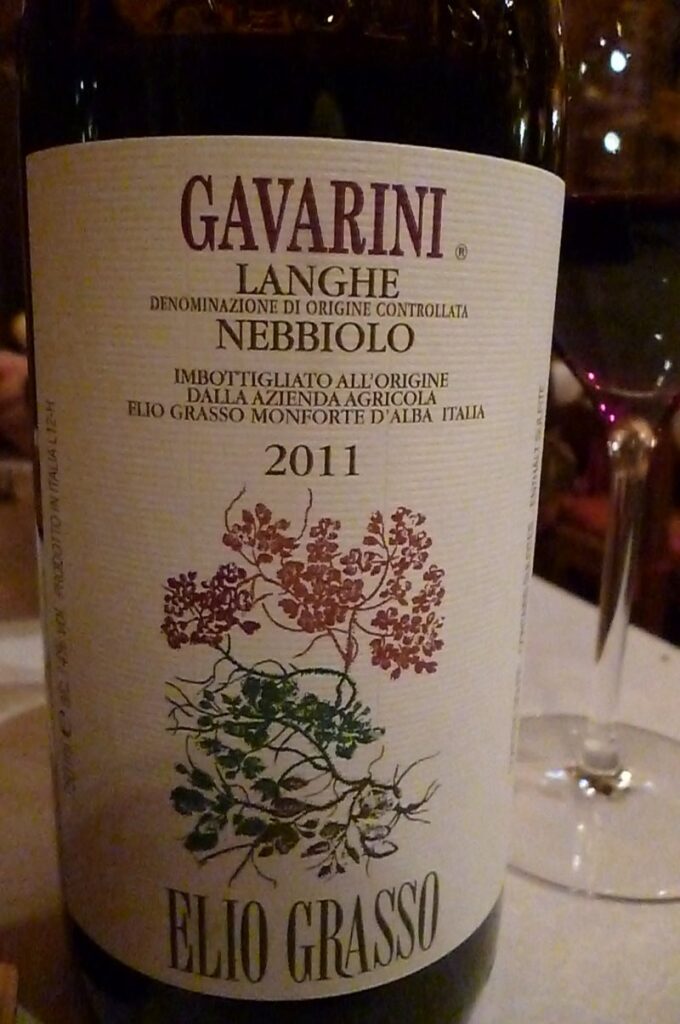娘が生まれやっと落ち着いてきたところなので、産休中の勤務先へ挨拶がてら食事へ。
もっと早く食べに行きたかったのだけど、妊娠中は例の食事規制がありお肉の半焼きや卵、無殺菌のチーズなどが食べれなかったし、産後直ぐは娘の愚図り具合も分からなかったので、誕生2ヶ月祝いも兼ね久々のレストランディナー。

付き出しアペタイザーは、
塩味のパンナコッタ(手前)
トマト風味のサブレとアンチョビ&玉ねぎのフォカッチャ(中央)
自家製黒トリュフバター

Sancerre La grande Cote 2011
Pascal Cotat
この夜は山岳部なのに爽やかな涼しさが無く、きりりとした白が飲みたかったので白ワインを。
フランス・ロワール地方、サンセールのソーヴィニヨン・ブランを。
パスカル・コタ社
サンセール ブラン ラ・グランド・コート 2011
樽発酵、樽熟成後、乳酸発酵、濾過処理は行わず、月の満ち欠けによる瓶詰め、自然の恩恵を大事にしたビオデナミ農法で造られているワイン。
野生のハーブ、アスパラガス、柚子のような仄かな苦味の柑橘類、複雑で濃厚な味わい、キリッとしたミネラル、お肉料理にも良く合いました。

La dadolata di vitello con le sue salse
この界隈はブランド牛「ファッソーナ」の産地。
この肉を一口ずつ味わってもらう一品。
赤身の柔らかくコクのあるファッソーナ牛はあっさりして食べ易いので、脂身たっぷりの日本のお肉が苦手な私にぴったりのお肉。

Torcione di fegato grasso di Fassona, Marrin glacé, pistacchi, nicciole e sorbetto alla mela cotta
マロングラッセ、ピスタチオ、ヘーゼルナッツで包みこんだファッソーナ牛のフォアグラ 焼きりんごのシャーベット添え

La melanzana perlina gusti parmigiana
トマトとチーズの詰め物入り茄子のオーブン焼き バジリコ風味のジェラートと共に

Risotto all’aglio orsino, il bruss e le nocciole
Aglio orsino 和名ラムソン。
チャイブの近縁種でニンニクの香りがし、葉を食用にしペーストにしたり、刻んでバターに練り込んだりして使用。
緑鮮やかなラムソンのリゾット ブルッスチーズとヘーゼルナッツ

Spaghetti trafilati aringa, salsa carbonara e pepe lungo assam
スパゲッティ・カルボナーラ 「ナッツィオナーレ風」
濃厚なカルボナーラソースを卓上にて麺の上にかけてくれる一品

Chateaubriand di Fassone
Carrello caldo con tagli di carne
メイン、セコンドピアットは私達が頼んだものはファッソーネ牛のシャトーブリアン。
保温のついたワゴン、目の前でサーヴしてくれます。


オーナーが厳選したチーズの数々。
ほとんどが私が住んでいるこの界隈で作られているもの。

Latte e pollini
デザートはレストラン近郊で作られている乳牛を3種仕立てにし、フワフワの綿菓子を添えたもの
遊び心のあるお皿ですが、濃厚な味わい、地元料理。

食後のプチ・フール。
木の温もりのあるレストラン、娘もおとなしくスリングに中で丸まってくれてたので久々ののんびり、まったりの食事でした〜。
Ristorante Nazionale
Via Cavour 60 Vernante
017-1920181