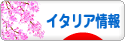先日、ピエモンテワイナリーの視察のため、インポーターさんの来訪あり。
ワイン街道と呼ばれている、バローロ脇の県道を通り北上し、目的地のアスティ県、ニッツァ・モンフェラートへ。
(上記写真)バローロ村と、イタリア黒葡萄代表品種、バローロやバルバレスコを造り出すネッビオーロ種。
今春例年より降雨量が多く、葡萄の生育、病害の危険等、この時季の気象が悪ければ、収量や品質に大打撃なので、栽培者は冷や汗をかいていたようですが6月は天候も良く順調に育っているとのこと!!!
ニッツァ・モンフェッラートからは、ドルチェット種、バルベーラ種、モスカート種の畑を。

(上記写真)ドルチェット種。「ちょっぴり甘い」というネーミングで響きのよい黒葡萄。
勿論辛口ですが比較的酸が少なく早飲みタイプで、南ピエモンテ人のディリーワイン
とし愛飲されている品種。
此処、モンフェッラート地区を中心にアレッサンドリア県(ピエモンテ州)、クネオ県(ピエモンテ州)と広範囲に渡り栽培されており、リグーリア州の西リビエラ地方では、オルメアスコ種という名で栽培されています。
ネッビオーロ種と比べても分かるように、葉っぱは丸みを帯びているのが見分け方の特徴だそうです。

(上記写真)バルベーラ種。
他の品種に比べ蔓が柔らかくて厄介ものなのだそうです。
新梢が密集すると、風通しや日当たりも悪くなるので余分な葉を取り除いたり、垣根に絡ませたり、ワイヤーに結束したりする作業をこの時季に繰り返しているのとのこと。
特にこのバルベーラ種には難儀しているみたいでした。
6月下旬に実止まりをよくするため、新梢の先端を切り伸びを止める作業が一斉に行われます。
8月、一つの幹から良質な5つの房を選び、その他の房は全て切り取り、実の調整をするのだそうです。
案内してくださった生産者さんは、バルバレスコ村で有名なガイア社のワイナリーで9年間勤務後、実家が経営する葡萄農家の後継者に。
全部で7ヘクタール所有とのことで、化学肥料や殺虫剤を使用しない自然農法で整備された畑は手間と根気がいるお仕事です。

(上記写真)モスカート種。イタリア全土で栽培されているマスカット。
アスティ県で生産されるものは、発泡性ワインのアスティ・スプマンテもしくは、独特のアロマを活かすため、アルコール発酵を抑えた弱発泡性のモスカート・ダスティが造られていて、飲みやすいモスカート・ダスティは、私の周りでも大好評です。

途中で立ち寄った、生産者さん宅の畑のサクランボの木。
本当の豊かさや美しさとは何かを教えてくれるイタリア暮らし。
自然と寄り添う暮らし・・・自然とイタリアはこれからもずっとずっと共存し続けてほしいと思う今日このごろです。